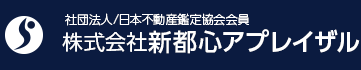コラム~第77回「建物の固定資産税評価」
2025.10.7
建物の固定資産評価は、不動産鑑定士が評価するのではなく、市区町村の建物固定資産評価担当が評価することとなっている。ただし、建物を新築した場合、都道府県が不動産取得税を先に課税することとなるので、基本は、建物の固定資産評価は、都道府県の建物固定資産担当が評価している。
その不動産取得税の固定資産税評価額をもとに各市区町村にその価格が引き継がれることとなっている。そして、市区町村については、都道府県が評価した新築の建物の固定資産税評価額を新築した翌年1月1日の価格として、新築後半年経過しているとして経年減点補正(いわゆる減価修正)を行い、評価していることとなっている。したがって、市区町村の固定資産税評価額は、新築価額ではなく、中古建物として評価されていることに注意したい。
次に、3年ごとに再建築価額(新規に建物を建築した場合の価額)を計算して経年減点補正を行って建物の固定資産税評価額を評価している。
そこで、注意したいのは、評価替えの年度では、前年固定資産税評価額と評価替えした年度の固定資産税評価額と比較して、どちらか低い方を採用することとなっている。
建築費が上昇している時期は、評価替えの固定資産税評価額が高くなることにより、前年の固定資産税評価額が低くなり、前年の固定資産税評価額が継続することとなる。
そうすると新築後の評価した固定資産税評価額が継続することとなり、減価するはずの固定資産税評価額が変わらないという珍現象が生じている。まあ、納税者有利なので、文句はつけられないが、相続税評価では、建物は固定資産税評価額となっており、時価との乖離が著しく問題といえば問題である。