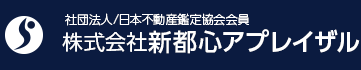コラム~第73回「規模格差と中小工場地区」
2025.9.17
相続税法財産評価基本通達では、平成30年から広大地通達が廃止され、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設され、地積規模が大きな宅地については評価の大きな改正がなされた。
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなっており、中小工場地区は外されている。
中小工場地区になっているのは、用途地域では、準工業地域、工業地域が中心となっており、商業地域と住宅地域の中間的な商住混在地域となっており、価格水準も住宅地域とほぼ同等となっている。しかし、税務上で中小工場地区と認定されれば、例えば500㎡の土地が中小工場地区に存在しているか普通商業・併用住宅地区に存在しているかで相続税評価額が雲泥の差となる。
税務上の中小工場地区の考え方は、全国の準工業地域、工場地域にある地価公示価格の平均値を算出し、その価格が隣接する住宅地域の価格の半分程度となることから、「地積規模の大きな宅地の評価」から対象外としたといわれている。
全国平均値ではそうなるであろうが、東京圏、名古屋圏、大阪圏の準工業地域、工場地域では、周辺の住宅価格よりも高い水準にあり、そのような地区で「地積規模の大きな宅地の評価」を認めなければ、隣接する地区での相続税評価額の価格差が顕著となり、課税の公平さが保たれていない現状がある。
是非とも、改正から7年を過ぎて「地積規模の大きな宅地の評価」を改正する必要があるものと提言したい。