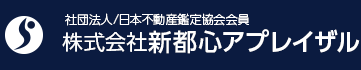コラム~第69回「無道路地」
2025.8.1
「無道路地」というと、一般的に「道路に接していない土地」と理解している方が多いが、正しくは「建物が建てられない土地」または「既存建物の建て替えができない土地」のことをいう。道路にまったく接していない土地以外にも、道路に接していても建物が建てられない土地も「無道路地」となることに留意したい。
相続税評価通達では建物が建てられない土地はいわゆる「接道義務を満たさない宅地」として「無道路地」の中に含まれており、「道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう」と記載されています(評基通20-3(注1))。
土地の価値は建物の建築の可否によって大きく変わるので、評価対象地が無道路地かどうかは評価の入口の段階で判断することとなる。
また、無道路地かどうかを見極めるためには、「接道義務」について理解しておく必要がある。
「接道義務」とは、建築基準法その他の法令、条例等において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件であり、都市計画区域内及び準都市計画区域内では、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」とされている(建築基準法第41の2、43)。
逆にいえば、都市計画区域外なら道路に接していない土地でも建物が建てられるということで、都市計画区域外では無道路地という概念はない。テレビの番組で「ぽつんと一軒家」となるものがあるが、山の中で家が建っているのは都市計画区域外の地域であり、自由に家が建てられることとなる。
この接道義務は、都道府県、市町村等の条例で独自に規定されている場合もあるので注意が必要だ。
例えば、「東京都では接道義務を満たす土地だが、横浜市では満たさない土地」ということがある。また、2m以上接道していても、その道路が「建築基準法上の道路」でなければ、接道義務を満たしているとはいえず、家屋を建築することができない。したがって、接道義務を満たすとは、「建築基準法上の道路に2m以上接している」ということになる。