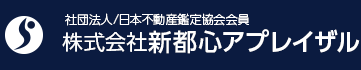コラム~第67回「土地価格比準表」
2025.7.7
土地価格比準表は、昭和50年1月20日付け国土庁土地局地価調査課長通達「国土利用計画法の施行に伴う土地価格の評価等について」により創設された。
この土地価格比準法は、国、地方公共団体が国民から用地買収等の適切な施行のため、地価公示地等からの統一的、合理的な比準(要因比較)方式の確立を目指して作成された。その後昭和60年以降、土地バブルが発生し、そのバブルを沈静化するために国土利用計画法の適用が強化され、昭和62年に土地を100㎡以上売買する場合、事前に市区町村に取引価格を届出する義務が課され、許可を得ないで土地売買をすればその仲介業者は公表されることとなった。そこで、この土地価格比準表は、土地格差補正率として活用されていた訳である。
しかし、バブル崩壊後、土地の価格規制は必要となくなり、届出制も現在は、市街化区域で2000㎡以上の土地取引については事後的に届出制となっているのが現状である。
また、その格差率についても、不動産鑑定士において、参考程度でしか使われていない。使われているのは、損失補償の際の土地評価(国土交通省損失補償取扱要領別記1「土地評価事務処理要領」)程度である。
ところで税務評価では、裁決判決において、その土地価格比準法が使われている。取引事例を分析する場合、その格差率を利用して鑑定評価における取引事例の格差率の妥当性を主張する例が多い。しかし、土地価格比準表の格差率表は、大分類の格差率評価であり、個別性に欠け鑑定評価には不向きである。例えていえば、日本不動産研究所の六大都市の市街地価格指数に近く、俯瞰した全体を把握するには有用であるが、範囲の狭い地域においてはその補正率を利用するには難しいものであり、税理士等が評価する場合には注意を要したい。