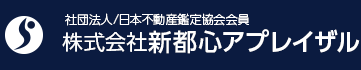コラム~第64回「共有減価」
2025.4.8
実務的に土地が共有の場合、共有者が他の共有者の持分を購入する場合がある。その共有の持分の価格を評価する場合、共有減価を考慮するかどうかは難しい問題である。
鑑定評価では、共有減価については議論が多く、共有であるために単独で意思決定ができず、管理の多様性、処分上の制約がある等の理由により市場減価が生じる場合もある。 また、不動産市場では共有減価を認識しないで取引されるケース(区分所有建物の敷地共有持分等)もあり、共有物分割のケースに限っても最高裁の判決(最高裁平成8年10月31日第一小法廷判決)にもあるとおり、依頼目的や取引当事者の事情によっても求めるべき価格が変わってくる可能性がある。
さらに、共有持分を購入して、「最終的に一人に帰属する」こととなる場合には「限定価格」という捉え方も可能であるために、共有減価が認識されると思われるケースで一般に存在する市場価値よりも上回った評価額を査定しても、公平性を害することはないと考えられる。
したがって、鑑定評価においては、共有減価が認められないわけではなく、ケースにおいては認められる判決もあり、また限定価格になると共有増価も考えられることから、評価においては、マーケットの動向や共有物の分割の結果、それが最終的に誰に帰属するかなど、依頼目的をよく認識し、公平の観点からどうあるべきか(共有減価を評価に反映させるべきか否か)を判断し、依頼者に前提条件を確認した上で 評価を行う必要である。