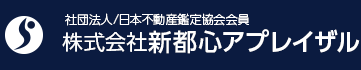コラム~第62回「相続後の売却価格」
2025.3.13
相続後、相続で取得した土地を売却することがある。基本的には、利害関係者間での売却価格は恣意性がありその価格の妥当性が問題となるが、第三者間での売買価格については通常の時価として認められる。ここでいう時価とは、唯一絶対価格でなく、適ストライクゾーン価格である。そのストライクゾーンについては、曖昧でありその把握は難しい。戸建住宅、マンション一室等については、取引事例が多く、その適正時価を判定することが容易であるが、商業ビル、地積規模が大きな土地、ホテル等の土地については、ビジネス不動産であることから購入者に多様性があり、そのストライクゾーンは広くなるであろう。また、不動産業者が購入することもある。不動産業者は、仕入値として購入することも多いので、時価よりも安く購入する。その仕入値は適正時価であろうか。税務上では原則認められない。しかし、不動産市場では多様性があり、特に収益物件については、その仕入値も適正時価の範囲内と思われる。
相続税法においては、売り急ぎ、買い進み等の事情がある場合にはその売買価格は否認される。鑑定評価でもそのような事情があれば時価としてはみなされていない。しかし、実務上は売り急ぎ等の事情があるかないかの判断については難しい。また、税務上の裁決判決では、1年以内の取引はおおむね時価として認められるが、1年以上の売買価格については否認される例が多い。いわゆる時間的な制限が設けられている。しかし、1年以上の売買価格は時価を表していないであろうか。1年以上売買が成立しないことは、売買が難しい地積規模な大きな土地や山林等の売却が困難な特別な土地である。そのような土地について1年以上経っているから時価と認めないとの判断はいかがなものであろうか。
実務的には、その売買価格が適正時価であることを不動産鑑定士の鑑定評価により立証することで認められるケースもある。
そこで、私見ではあるが、相続税評価において路線価をもって価格を統一するのではなく、適正時価はストライクゾーンであることを認め、例えば、路線価の70%以内であればその売買価格を認めるという現実に即した運用をすべきであろう。