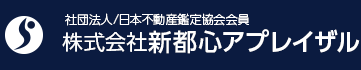コラム~第61回「財産評価の時価問題」
2025.2.27
相続の遺産分割においては、財産の評価は時価が原則である。時価とは、通常の時価であり、鑑定評価が基本となる。
しかし、実務的には、相続税の申告が必要であり、税務上は財産評価基本通達により求められたみなし時価として相続税評価額で計算している。
その価額は時価と異なることではあるが、便宜的に時価と見なして利用していることが多い。
家庭裁判所においても基本は時価であり、申立人、相手方は時価を主張することができるが、時価を主張する場合、鑑定評価書が必要となり、時間と費用がかかるので不動産業者の査定書等が利用されるが、その査定価格は時価とはいえず、双方協議となり、当事者で折り合えば、その価格を前提に協議となるが、現実では、双方が合意するのであれば相続税評価額も利用することが多い。
そこで、問題となることは、相続税法の時価と鑑定評価の時価概念が異なることとなるので注意する必要がある。
例えば、相当地代を支払っている場合の土地評価、無償返還届出を提出している場合の土地評価については、その時価が異なることである。
相当地代、無償返還届出等の規定は税務評価では成立するが鑑定評価では認められない。鑑定評価では、借地の場合、借地借家法を前提として評価することとなるが、税務評価では、関係者当事者間の特別な評価であり借地借家法を外して評価されている。遺産分割の時価は、鑑定評価の時価となるために借地借家法を前提とする価格となり、税務評価と鑑定評価では、その価格概念が異なることに注意をしたい。